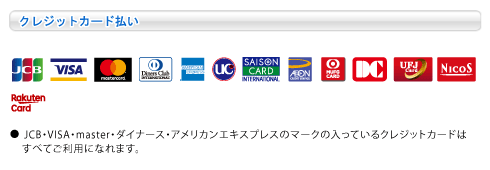お位牌は故人を思いながら、毎日手を合わせる大切なものです。
故人にふさわしいお位牌を選ぶにあたって、たくさんの種類の中から選ぶ時のポイントをご案内いたします。
お位牌の大きさは、ご本尊様より少し小さくすること、ご先祖様のお位牌と同じか少し小さい位のお位牌を選ぶことが一般的です。お位牌の形や材料は、宗派によって決まっていませんので、自由にお選びいただけます。
(ご先祖様のお位牌と同じものを希望される際は、お位牌の写真と寸法をご用意ください。)
初めてお位牌を作られる場合は、あわせてお仏壇のサイズも考えると良いでしょう。
先にお位牌を決めてしまうとお仏壇の中にお位牌を安置されたときにバランスが取れなくなってしまいますので注意が必要です。お仏壇をしばらくご用意できない方も、お仏壇をどのくらいのサイズにするかを考えて、お位牌を決めてください。
お位牌は故人の方そのものとして、お祀りするようになりますので、故人を想いながら家族の皆様で選ぶことをお勧めいたします。
宗派によっては戒名の上に梵字を入れることもありますので、自分の家の宗派が何かも確認しておく必要があります。
お位牌の戒名の記し方は、機械彫りと機械書きの二通りから選べます。
多くのご先祖様を、たくさんお祀りし続けるとお位牌が多くなり、お仏壇の中が手狭になってしまいます。そうした場合は回出位牌に合祀することにより、一基のお位牌でお祀りすることができます。
回出位牌は、お位牌の札の部分が箱状で、中に戒名などを書き記した木札を10枚程度納める事ができます。日ごろは○○家先祖代々と書かれた札を一番手前に出し、命日や法事の時に、個々の御霊の札を前面に出してお祀りすることができます。
夫婦のお位牌を祀る場合は、個別に祀る方法のほかに、夫婦二名書きのお位牌にする方法も年々増えてきております。
夫婦位牌は、お位牌を新しくつくるので、文字が薄れたり、お線香のヤニなどでお位牌がくすんで見劣りすることもありません。
また、仏壇内の限られているスペースを確保することもできます。
宗派、地域などによりできない場合もありますので、菩提寺のご住職様に確認を取るようにしてください。
位牌分けなど兄弟姉妹で同じお位牌をお考えの場合、宗派、地域などにより出来ない場合もありますので、菩提寺のご住職様に確認を取るようにしてください。
なお、無宗派の方で位牌分けをご希望の方は、お祀りする気持ちが一番大切なので、ご家族の方々で話し合ってお決めください。
位牌へ記す文字のレイアウトを決めます。
一般的には表面に戒名を記し、裏面に俗名と寂年齢(数え歳)を記します。
寂年月日は、表面または裏面のどちらかに入れます。
ご先祖様のお位牌と同じ形式でつくる場合は、文字の使い方やバランスなどに気を付ける必要があります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |