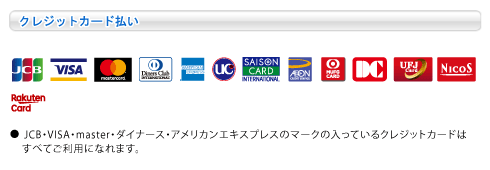普段の生活の中で、お位牌を作るという機会はなかなかございません。
しかし、ご不幸は突然やってきます。
ご葬儀を終えられて、あっという間に過ぎてしまう時間の中で、訳もわからずお位牌を作ってしまい、納得がいかないという方々が増えているようです。
お位牌は故人のお姿です。数ある種類の中から満足のいくお位牌作りができるよう、中居堂ではお位牌製作のお手伝いをさせていただいております。
お位牌は基本的には四十九日の法要までに用意しなければなりません。
しかし、ご葬儀後も各種手続きや後片付けなどで時間に追われ、なかなかお位牌を作ることができません。法要があと数日に迫り、あわてて仏具店に駆け込みますが、お位牌の種類やサイズがたくさんあり過ぎて、なかなか決めることができません。また、決まり事等もあることから、一度自宅に戻って、色々調べ直ししてから再度お店に出向くという二度手間になるケースもあります。
そこで、こちらではお位牌を新しくお作りになる際に、事前に準備しておくとスムーズにいく納得の選び方のコツをご案内致します。

お位牌を初めてお作りになる場合は、はじめに安置するお仏壇を決めると良いでしょう。お仏壇はご先祖様の自宅のような存在です。その自宅の大きさが明確でなければ、どのくらいのお位牌を作れば良いのか、店舗に来店してもはっきりしません。そのため、まず初めての仏様の場合は大まかなお仏壇のイメージとお位牌とのサイズのバランスを明確にすることをオススメ致します。
また、元からご先祖様のお位牌がある場合は、新しく作るお位牌はご先祖様より大きくならない、もしくは同じ位の大きさでお位牌を作らなければなりません。
そのため、新しいお位牌を作る際には、ご先祖様のお位牌の寸法を明確にされるとスムーズにお位牌をお作りいただけると思います。
※採寸のポイント
採寸は右図のように『総丈』『札部分の高さ』『札部分の幅』『台の高さ』などを測ってください。
初めてお位牌を作られる場合、何もわからずに仏具店にご来店されるケースがほとんどです。お位牌を作る際に、必要な段取りがあります。
・ご葬儀で用意された白木のお位牌を準備する(もしくは白木のお位牌の写真を用意する)
・作りたいお位牌のサイズを明確にする
・ご先祖さまのお位牌がある場合は、現物のお位牌を店舗に持参する(サイズを明確に採寸されている場合は写真でも大丈夫です)
・戒名を確認する(梵字、位などを菩提寺のご住職様に確認する)
・四十九日の魂入れの日を菩提寺に確認する
以上の点を踏まえた上で、店舗にご来店もしくはオンラインで注文されるとスムーズに進めることができると思います。
お位牌は同じような形をしたものがたくさんあります。通常 新しくお位牌をつくる場合は、ご先祖さまのお位牌と同じ種類で作るケースがほとんどです。しかし、見た目はほとんど同じでも漆塗りの質や、国産仕上げと海外仕上げの違い、金紛金箔の違いなどで金額は大きく変わってきます。
一度作ったらずっと手を合わせ続けるお位牌ですので、納得のいくお位牌選びをオススメ致します。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |