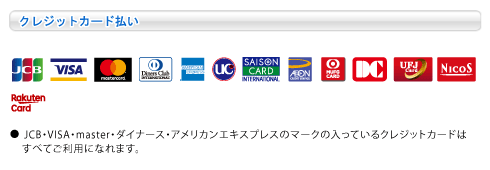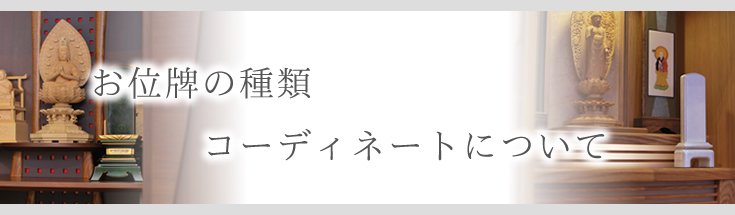
お位牌には、伝統的な形のお位牌から現代の形で表現したモダン位牌まで、たくさんの種類が存在します。
こちらでは、その中から大まかな種類のお位牌をご紹介致します。

白木位牌とは、本位牌が完成するまでの仮のお位牌のことです。
葬儀の時、祭壇の上に安置するための仮位牌のことを白木位牌といいます。
何も施されていない白木のままのお位牌で、享年や俗名、戒名などが書かれています。

塗り位牌は昔からの伝統的なお位牌の形になります。
白木に漆を塗り、金箔や金粉を施し完成したお位牌を塗り位牌といいます。
種類は大まかに3種類あり、塗り位牌(艶消し位牌)、上塗位牌(艶がある位牌)、呂色位牌(高級漆仕上げ位牌)の種類で分かれています。
最近では、輪島塗や津軽塗、蒔絵入りなど特有のお位牌なども作られてきています。

唐木位牌は、高級銘木である黒檀や紫檀の無垢材を用い木目を生かしたお位牌です。
極めて硬く、耐久性に優れているのが特徴です。
お仏壇の材料として唐木が用いられてきたことから、漆を施さずにお仏壇の質感と合わせて作ることのできるお位牌として扱われてきました。
唐木は非常にお手入れのしやすい材料であることから、昔から人気があるお位牌です。

最近の生活習慣にマッチしたモダン仏壇を選ばれる方が増えてきている中で、
それに合わせてコーディネートができるお位牌としてモダン位牌が作られています。
伝統的なお位牌の意味合いを残しながら、シンプルでお洒落な形で、現代にマッチしたお位牌として人気があります。

お位牌が増え、お仏壇の中に安置できなくなってきた際に、先祖代々のお位牌をひとつにまとめて作るお位牌です。
お位牌の札の部分が箱状になり屋根や扉がついたもので、お位牌の中には、札板を10枚程度収納できるようになっているお位牌です。
また、札に限らず過去帳式の回出位牌も作られています。
お位牌にはたくさんの形や種類があるように、お祀り方も様々なシチュエーションがあると思います。
そこでこちらでは様々なシーンに合わせたお位牌の祀り方をご紹介したいと思います。

日本の生活様式は様々な形に変化していますが、代表的な様式として和室があります。
昔から和室には仏間が設けられ、伝統的なお仏壇が安置されてきました。洋間も増えてきて
仏間を設けるケースは減ってきてはいますが、仏間がなくてもお仏壇を和室に安置する習慣はまだ続いています。
この和室には、従来型のお仏壇から現代型のモダン仏壇まで幅広く安置されています。そのお仏壇の中にお祀りするお位牌も、お仏壇とお部屋に合わせてお選びしたいところです。
現代型のモダン仏壇を和室に安置すると、少し洋風テイストにデザインされたお仏壇であってもお部屋の雰囲気とうまく調和して、お部屋がお仏壇の重厚感を引き立たせてくれます。
その良い雰囲気を演出しているお仏壇の中には、高級感のある伝統的な塗り位牌や重厚感のある唐木位牌をお選びすることをオススメ致します。
すべてモダンテイストで揃えるよりも、日本の和を重んじるようなアクセントをつけて、今どきの和室にコーディネートをしてみるのはいかがですか?

現在のライフスタイルはマンションなどが増え、どんどんコンパクトな生活が増えて来ています。生活スペースが限られて来ている中で、ご先祖さまの安置場所も限られてきます。
この限られた中で仏様は人目に出したくない、できれば陰に安置したいと考えている方々はたくさんいらっしゃいます。
しかし、ご先祖さまは決して陰に安置されることを望まれていないと思います。ご先祖さまは各家庭に必ず存在し、その家庭がいつまでも繁栄することを想い、いつも私たちの生活を見守っていらっしゃいます。
そこで、ご先祖さまをもっと近くで感じていただくことをオススメしたいと思います。
現代のご供養の形は変化を繰り返し、モダンなお仏壇、モダンなお位牌がライフスタイルに合わせてご用意されています。
皆さんが集まるリビングに、違和感なくコーディネートができるモダンなお仏壇とお位牌でもっと近くに仏様を安置してみてはいかがですか?

「お父さんは本当に立派だった」
「お婆ちゃんは最後までお洒落だったよね!」
身内の方がこの世を去り、残された家族からはいつもこのような言葉が行き交います。
亡くなられた故人には、必ずイメージがあり、どんな方だったのかも含めて戒名が授けられます。
この戒名が亡くなられた世界でのお名前となり、後世に代々残されていきます。
そして、故人の最後のお姿がお位牌となります。
お位牌の種類や形は様々で、これでなくてはならないという決まりもありません。
お位牌のデザイン、クオリティ、色合いなどで故人を連想させるお位牌選びをオススメ致します。

今まで全然考えたこともなかったご実家にあるお仏壇。
いつも当たり前のようにお盆休みにはお墓参りをし、お仏壇の中に祀られているご先祖さまに手を合わせてきました。
そんなある時、実家のお仏壇を自分が継承しなくてはならなくなったというケースがたくさん見られるようになってきました。
核家族化が進み、実家には年に何回かしか戻らないという生活環境の中で、実家に祀られているご先祖さまの継承はある日突然やってきます。
自分の菩提寺にはお墓参りに行っていたが、宗派がわからない、ご本尊って何かわからない、祀られているお位牌の中に知らない名前がある等の解決しなければならない事がたくさんあります。
そうなってしまう前に、ご先祖さまの継承もしっかりご自分のご両親やご親戚の方と前もって話し合っておくことをオススメ致します。
継承する際には、古くなったお仏壇を買い換える、お位牌がたくさんあるのでご先祖さまをまとめて祀ることができる回出位牌に作り変える、ご夫婦をまとめて一本の夫婦位牌にする等のたくさんの方法があります。
今一度、ご自分のご先祖さまをしっかり見つめ直し、ご先祖さまが喜ばれるご供養をしてみてはいかがですか?
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |